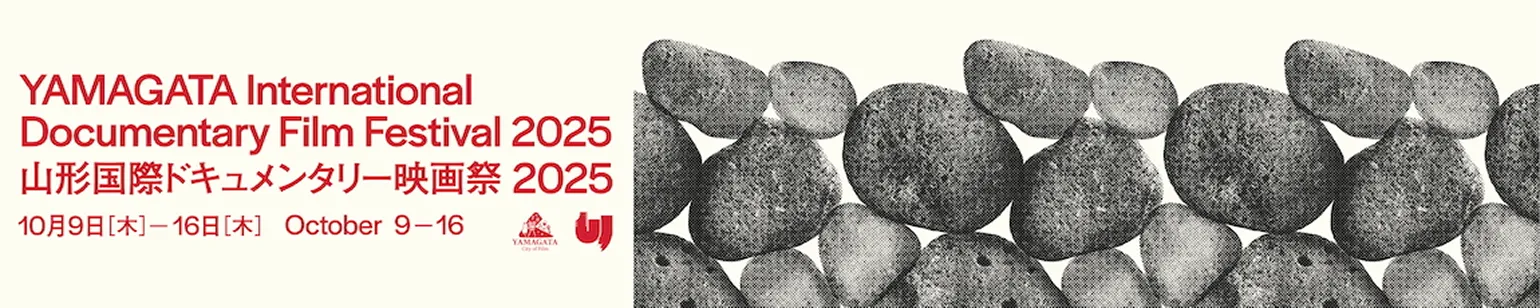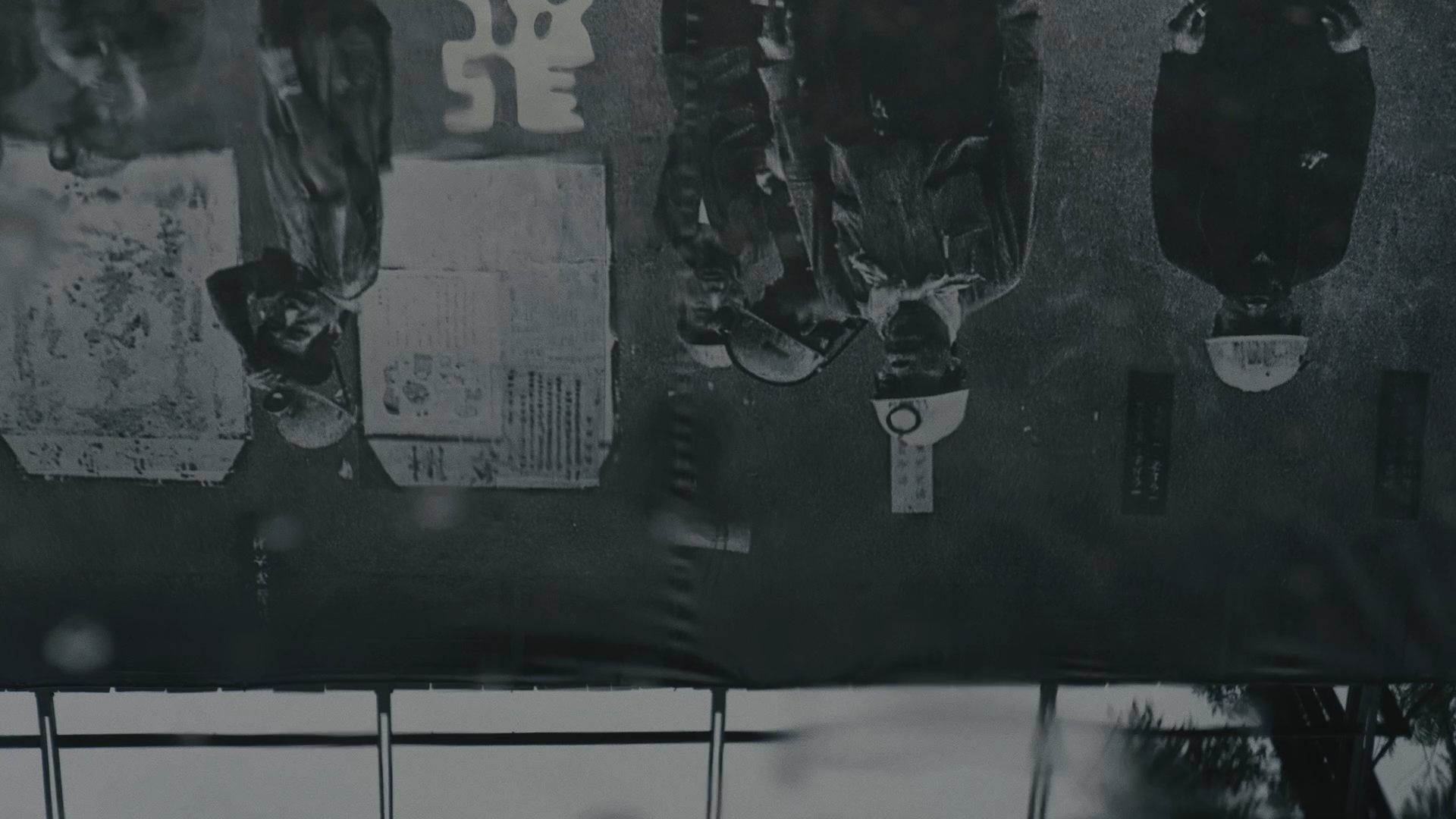
深い森を映し出すスクリーンに目をこらすと、地を這う電線が幾重にも重なっている。手持ちのカメラはそのまま脇に積まれた石垣を捉え、そこに穿たれた穴の向こうに草地を望む。続くひび割れたアスファルトを見下ろすカットでは、画面の右側で一本の太い線が赤く鈍い光を放っている。炭鉱の風景を見慣れた者には、それがかつての線路の跡だとすぐにわかる。これら冒頭の一連の映像は、今は無人となったその「場所」でかつて営まれていた人々の暮らしの気配を呼び起こす。
映画の構成自体はシンプルなもので、以上のようなプロローグを経て、7人の元鉱山労働者の名前と勤務歴などがテロップで一人ひとり紹介され、彼らの土地の霊にまつわる怪談めいたボイスオーバーが、ひとけを失った炭鉱の風景と重ね合わされていく。失われた「場所」にまつわる物語を映像で表現することについて上映後の質疑で問われた監督は、「80年代まで労働運動が禁じられた台湾では歴史が残りにくい状況だった。だからこそ炭鉱に関わった人々が今語る言葉に〈身体の感覚〉を持たせることを重視した」と語っていた。音と映像によってもたらされる〈身体の感覚〉とは、単純な過去の再現ではなく、記憶の裏付けでもない。
その感覚は、語りと映像が互いを補い合う構成にすることで現実離れした「語り」に具体的な空間の輪郭を付与し、不確かな物語にいわば仮初(かりそめ)の肉体を与えることによって生じる。一方で半ば死んでしまったかのように熱を失った現実のほうも、映像というパラレルな空間に置き換えられ、さらには「語り」というサウンドと交錯することにより、再び息が吹き込まれる。本作は、映像と音(語り)の交錯から成る新たな「場所」を立ち上がらせる試みなのだ。
この土地の名前(侯硐=猿の洞窟)の由来でもある猿を、生薬の材料にするために殺して木に吊るしていたという記憶が語られる背景には、かつて猿がいた山の遠望が廃屋とともに示され、木々に吊られた亡骸を想像させる。坑夫が博打で大金を無駄にし、選炭場の横を歩いて金を取りに自宅に戻る途中、亡霊めいた存在に出会う逸話には、観光客を乗せて坑内に入ろうとする荷車と、それに乗るためのチケットをもぎる女性の手元が描かれ、かつての坑夫の仕事ぶりと金の絡んだ日常に潜む影を暗示する。
語りの多くが「怪談」であるのは、炭鉱での仕事や暮らしが「死」とつねに隣り合わせであったからだろう。例えば、カメラが観光用の荷車に載せられ暗い坑道を進む映像には、坑内を支える梁の上の木材が軋む音に事故の予兆を見出し、間一髪で逃げおおせた体験が呼応するように語られる。続いて、語り手とともに事故の救助に向かうことを断った坑夫がその一月後に自ら事故に遭い、その死の直前に彼の身体を洗ってやったというエピソードには、かつて彼らが浸かっていたであろう浴室に光が差し込むイメージが重ねられ、カメラは外へと漏れ出る水の流れを辿り、未だ忘れ得ない死者の身体を浮かび上がらせる。こうした現在の空間を捉えたカットには時折、町の中心を走る電車の音が響く。かつて炭鉱を支えた線路は、最後の灯し火のように今もかろうじてこの土地に人を運び続け、この映画をも前進させるのだ。
それにしても、これらの語りは何を伝えようとしているのだろう。上映後、監督に地域の人々との関わりについて直接尋ねてみると、「彼らの遠い記憶は今や曖昧なものになっていて、話すことは毎回違っていた。この地で活動する研究者達が正史を描こうとするのに対し、私はあくまでもその言葉に霊感を得てこの映像を作った」という。
国内外の炭鉱を訪れ、今に至る空間の遍歴を客観的な図面や記録をもとに研究している私が土地に暮らす人々の話を聞く中で取りこぼしていた何かを、この映画は想起させる。何とか正しい情報を手繰り寄せようと努める私を、時にはぐらかすかのように彼らの口から洩れるとりとめのない語りは、こちらが期待していた事実に繋がらないがゆえに私を落胆させる一方で、だからこそ、その語りの在り方そのものに魅了されもしたとでもいえばいいか。それは、「正しさ」や「事実」に収斂されることのない「余白」の魅力である。一つの産業がその役目を終え、活気を帯びた生がそこから消え失せた後、その履歴は残された空間によってしか捉えることができず、しかもそれらの多くは失われていく。しかし、本作の作り手たちはそのわずかな残滓に宿る「余白」の魅力を取りこぼすことなく掴むことに成功する。
我々が失われた「場所」を経験するためには、残された空間だけでなく曖昧な語りを受け入れる、こうした「余白」が必要だ。現実と並行して存在する映像の中の空間は語りを湛(たた)えて、もうひとつの「場所」としてスクリーンに息を吹き返す。
成原隆訓
![ドキュ山ライブ! [DOCU-YAMA LIVE!]](https://www.yidff-live.info/wp-content/themes/yidff-live_2017/images/header_sp_logo1.png)