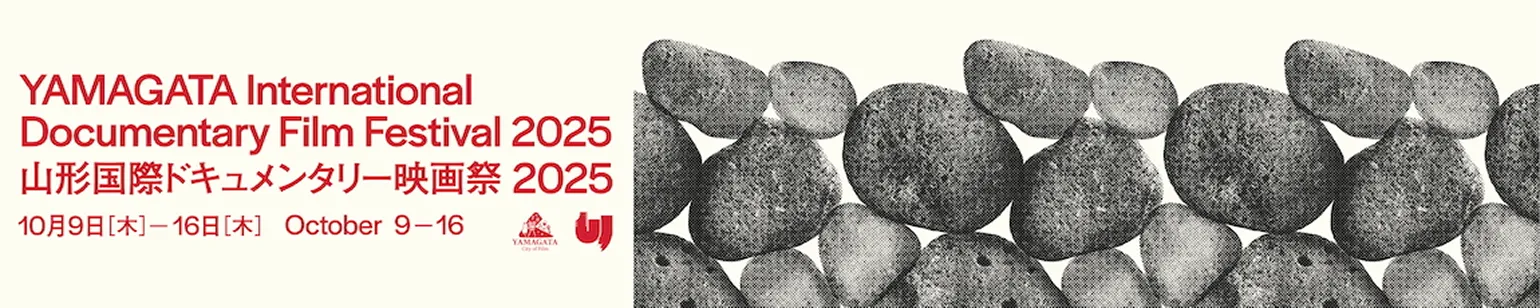手持ちキャメラと同時録音マイクでのインタビュー中に、「また税金が上がって…」などと屋外で愚痴を言う農夫らしき支持者の背後から不意に数名の男たちが扉を開けて登場し、そのまま画面の外へ出ていく。当の支持者から呼びかけられ、軽く冗談が交わされることで、私たちはその呼び止められた男こそがアメリカ合衆国大統領選に向けた民主党予備選挙中の候補者であることを知る。
今回の「アメリカン・ダイレクト・シネマ」特集において「1960−すべてが一変した年」なるプログラム内で上映された『予備選挙』(1960)は、その後の短くて他愛のない会話を経て候補者が次の遊説先へと慌ただしく向かうまでの一連の流れを切れ目なく捉えたショットから始まる。その画面に映っているのは、このあと本作で何度も登場する候補者ヒューバート・ハンフリーと、一度きりしか登場しない名もなき支持者の農夫で、これはあくまで候補者たちの選挙活動と選挙結果を伝える映画として制作された。それにもかかわらず、冒頭のシーンではハンフリー以上に農夫の存在が強く印象づけられる。
では、選挙戦のもう一人の候補者、若き日のジョン・F・ケネディはどのように映画に登場していたのか。初めて画面に現れるシーンで、ケネディは選挙スタッフに取り囲まれながらその間を縫うようにして演説会場の階段を駆け上がり、大挙して詰めかけた民衆の待つ壇上に到達する。割れんばかりの拍手と歓声が起こると、彼ははにかむような笑顔でそれに応え、誇らしげな笑みを浮かべるジャクリーン夫人がその傍らに立つ。のちに監督としてもダイレクト・シネマの重要作品を生み出すことになるアルバート・メイズルスは、持ち上げたキャメラを両手で支えながらケネディの動きを背後から追いかけ、壇上で彼の前に回り込むことで、ケネディの表情と民衆の熱狂を一つのショットで同時に捉えることに成功している。
熱狂する観衆の存在が、壇上に上がったケネディの存在と対等もしくはそれ以上に印象深く感じられるのは、そうした当時としては画期的な手持ちキャメラによる長回しや移動撮影の賜物だろう。機材に改良を重ね、この場面のような撮影や同時録音が可能になったことで、撮影スタッフは少人数で目立たないよう取材相手へ接近できるようになり、人の手足の細かな動きや表情のアップもその場の臨場感とともに捉えられるようになった。
映画はその後、両者の選挙活動をほぼ交互に追っていく。誰かれ構わず名刺を配って歩くハンフリーと、行く先々でサインをねだる若者たちに応じるケネディ。映っているのは候補者だけではない。彼らを支える民衆の姿がつねにそこにあった。メイズルスが撮った前述のケネディ登場のシーンが、先ほどは省略された部分も含め、さらに長いカットで終盤になって再び画面に映し出される。同じフッテージを二度使うことで制作者たちは、ケネディが文字通り当選への階段を颯爽と駆け上がっていく過程を映画の中で強調したかったのだろう。だとすれば、機材の改良や手法の改革を経たにせよ、この映画もまたいわゆる「有名人」とその栄光を描く古びた価値観の作品に過ぎないのか。
そうではないと私は考える。少なくとも私の目にこの『予備選挙』は、ケネディの存在と彼の活動をいわば「鏡」とすることで、彼を取り巻く民衆、彼ら一人一人の表情や熱狂をスクリーン(鏡)に見事に投影させる映画のように映る。制作者側の意図がどうであれ、この映画は、有名人であるケネディを主役にするかのようでいて、実はケネディに熱狂する民衆、つまりはどこにでもいる普通の人たちこそが時代の主役であることを観客に示すためにあり、それはまた、「有名人」の素顔や一挙手一投足をキャメラが捉えることができるようになったことで、彼もまた「普通の人」であることを明らかにするためにある、と言い換えてもよいのだろう。
ダイレクト・シネマは、有名人も一般市民も、それぞれが対等に映画の主役になることができると証明した。1960年が「すべてが一変した年」であるとすれば、まさしくそうした意味で捉えられねばならない。今こそ、時の為政者と一般の市民を区別することなく、たとえお互いに考え方が違う候補者であったとしても、同じ社会に生きる「隣人」同士としてフラットな目線でこの記念碑的映画を見てみようではないか(この考えはまた、ドキュメンタリー映画の作り手側として、取材相手を余計な色眼鏡で見ることなく、たまたま自分のそばにいて生活している「隣人」として接しようとする私の態度でもある)。ダイレクト・シネマ、誰がための映画か。
奥谷洋一郎
![ドキュ山ライブ! [DOCU-YAMA LIVE!]](https://www.yidff-live.info/wp-content/themes/yidff-live_2017/images/header_sp_logo1.png)